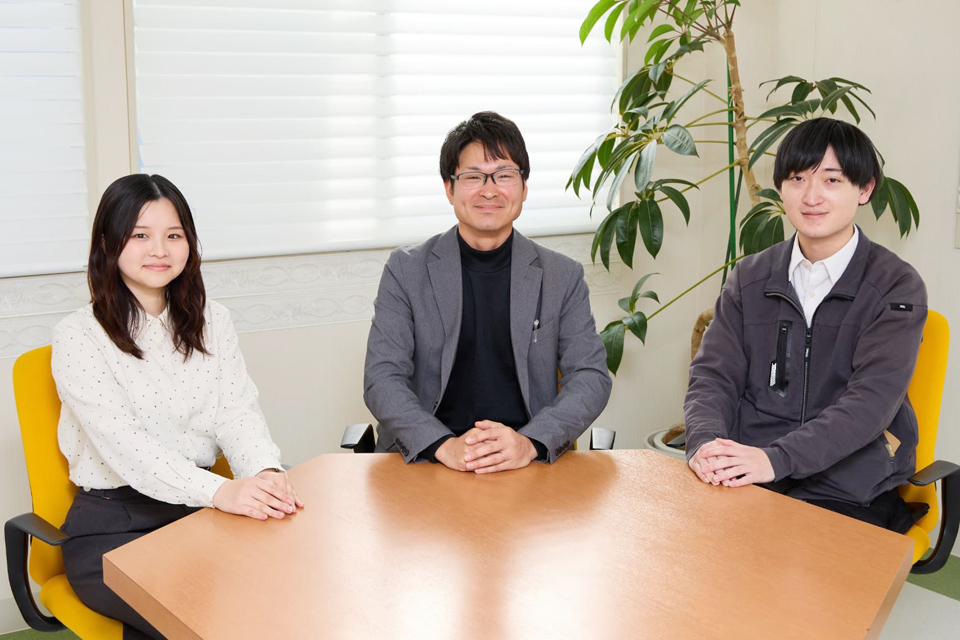ライフステージが変化しても、自分に合った働き方を選べる!
経験者が語る、ワークライフバランスを実現する秘訣とは?
PROFILE

Y・O
2000年に、さわやか社員として新日本ビルサービスに中途入社。当初はパート勤務で働いていたが、2005年後から正社員に。プロパティマネジメント事業部でショッピングセンターの管理・運営業務を約10年間経験した後、サポート本部へ異動。現在はサポート本部の部長として、総務全般の管理職を務めている。
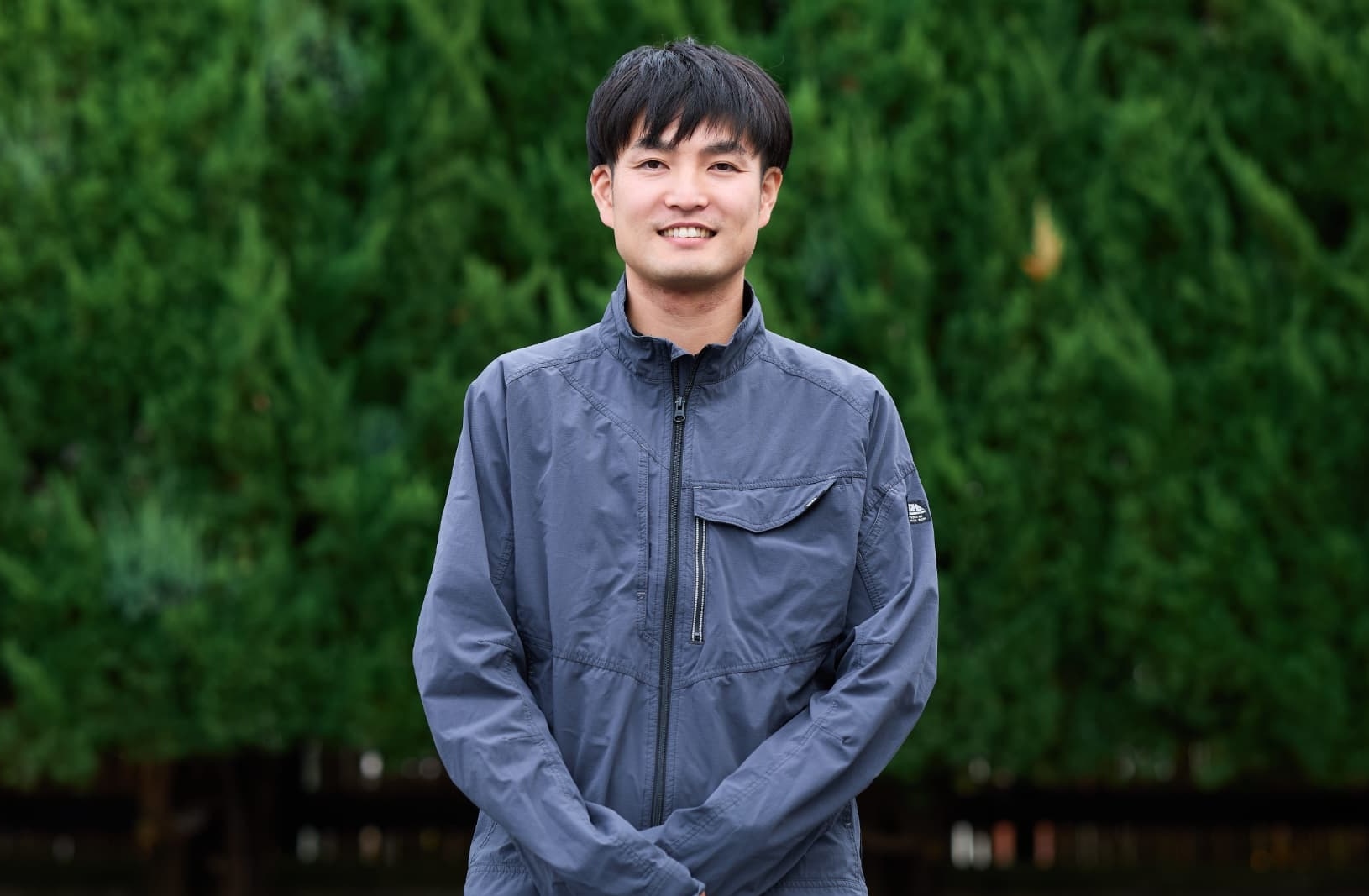
Y・A
大学卒業後、2012年に新日本ビルサービスへ新卒入社。入社後はファシリティサービス事業部に配属され、建物の法定点検を行うエンジニアとして活躍。現在は主に在宅勤務で、顧客担当営業のチーフマネージャーを務めている。

C・T
大学卒業後、2017年に新日本ビルサービスへ新卒入社。入社後は清掃部門の業務を経験したが、内勤に変更し、資材発注などの業務を担当。さらに、妊娠・出産を機に経理部へ異動し、育休復帰後は時短勤務で出入金や請求書の管理をメインに担当している。
育児・出産、高齢の親の病気や介護…。
その時々の状況に応じて働き方を変えてきた

―――長い職業人生の中には、ライフステージの変化や家庭の事情などによってキャリアプランの見直しを迫られる局面もあります。皆さんは、新日本ビルサービスでずっと働きながら、ご自身のその時々の状況に応じて働き方や仕事内容を変えてこられた経験をお持ちです。まずは自己紹介を兼ねて、それぞれの入社の経緯と、入社後の仕事内容について教えてください。
Oさん 私が当社に入社したのは、2000年のこと。同居している義理の母が定年を迎え、義母から「若いうちに外で働いた方がいい」と言われ、主婦業を交替して日中のパート勤務を始めたことがきっかけでした。当社が管理するショッピングセンターのテナント飲食店で働くうち、当社の担当者と知り合い、飲食店と掛け持ちで働くことに。その後、フルタイムで当社の業務であるショッピングセンターの管理運営に携わるようになり、5年後に正社員になりました。以降は長年、プロパティマネジメント事業部でビル管理やテナント管理などの業務を担当してきましたが、2020年にサポート本部へ異動。一般企業でいう総務部の業務に携わりました。現在はサポート本部の部長として、業務や部下の管理、社内の問い合わせ対応などの管理職業務を担当しています。

Aさん 私は東日本大震災が起きた翌年の2012年に、当社へ入社しました。震災の影響で就職活動を中断しましたが、幸い当社から早くに内定をいただき、「この会社なら自分で力をつけて、いろいろな仕事に挑戦できそうだ」と感じたことが入社の決め手でした。
入社後はファシリティサービス事業部で、建物の法定点検を担当。エンジニアとしての経験を積むうちに点検に伴う修理や工事も手がけるようになり、仕事の幅が広がりました。けれども、5年前に妻の里帰り出産と義父の病気が重なり、九州にある妻の実家で家族のサポートに専念したいという思いが強くなりました。上司とともにリモート勤務や在宅勤務が可能な業務を模索した結果、事務系の業務を担当することに。現在も、在宅勤務中心で働いています。
Tさん 私は大学では農業を専攻しましたが、就職活動では自分が好きなこと・得意なことである掃除を仕事にしたいと考え、企業を探しました。そんな中、当社の病院清掃(感染対策清掃)に興味を持ったのです。入社後は病院清掃の業務に就きましたが、途中で自分に向いていないと感じ、O部長とも相談した結果、内勤に変更していただきました。内勤では資材発注などの業務を担当していましたが、妊娠・出産を機に経理部へ異動し、育休復帰後は経理を担当しています。
一緒に働く仲間の理解と協力。
職場のサポートがあったから、仕事を続けられた

―――皆さんは出産・育児や家族の介護などのために、休暇や休業を取得されています。それぞれ、いつ、どのようにして休暇や休業を取得されていましたか?
Oさん 私の場合は、娘の産後のサポートと孫の世話をするための「孫育休」でした。私には娘が2人いるのですが、同じ年に2ヶ月違いで出産したのです。2人とも離れて住んでいるので、彼女たちの出産時にはそれぞれ5日間ほど休みをいただき、応援に行きました。その後も、娘と孫たちの世話のために時差出勤や早退、急な休みをいただくことがしばしばありましたが、一番大変だったのが2024年の夏です。長女の第2子の出産で1週間くらいの「孫育休」をいただいた後、しばらくして義母が突然、くも膜下出血で倒れたのです。義母はすぐ手術を受け、現在はリハビリ病院に入院していますが、病状が落ち着くまでの5ヶ月間くらいは、病院からの呼び出しや転院の手続きなどで急に出社できなくなったり、遅刻・早退せざるを得ないことが何回もありました。
Aさん 今となっては男性の育休取得も推奨されるようになり、希望すれば取得できる環境が整ってきましたが、2019~2020年当時は男性の育休取得は珍しく、業務の引き継ぎなども考えると完全に休むことは難しい状況でした。そこで、九州にいても可能な書類作成など事務系の業務を私が集中的に担うことにし、現場に出る業務はチームのメンバーにお願いする形で、リモート勤務を試みることにしました。まだコロナで緊急事態宣言が発出される前、リモート勤務が今ほど普及していなかった時代です。九州で約1ヵ月半、リモート勤務を実践してわかったのは、意外とできるということ。これまでチーム内に事務系の業務をメインに担当するメンバーはいなかったこともあり、現場系と事務系でうまく分担してチームの仕事を回すことができました。また、職場から離れていても、見積書の作成や電話、メールでの顧客対応など、私にできる業務はけっこうあります。この経験が布石となり、育休後も在宅中心で仕事をすることに。1年前からは仕事内容も変わり、顧客担当営業のチームマネージャーになりました。顧客訪問で現場に出る日もありますが、今も在宅勤務が中心で、育児をサポートすることができ、とても助かっています。
Tさん 私は2021年の2月に出産しました。前年12月の仕事納めの日を最後に産休に入り、子どもが1歳の4月に保育所に入園するまでの約1年間、産休をいただきました。産休復帰後は、朝9時から夕方4時までの時短勤務に。今のところ、子どもが小学校に入学するまでは時短勤務を続けたいと思っています。10歳までの時短勤務も可能な制度になっているので、様子を見てフルタイムに切り替えたいですね。
仕事と家庭を両立するための秘訣は、
業務効率化と「今日の仕事を明日に持ち越さない」気合い
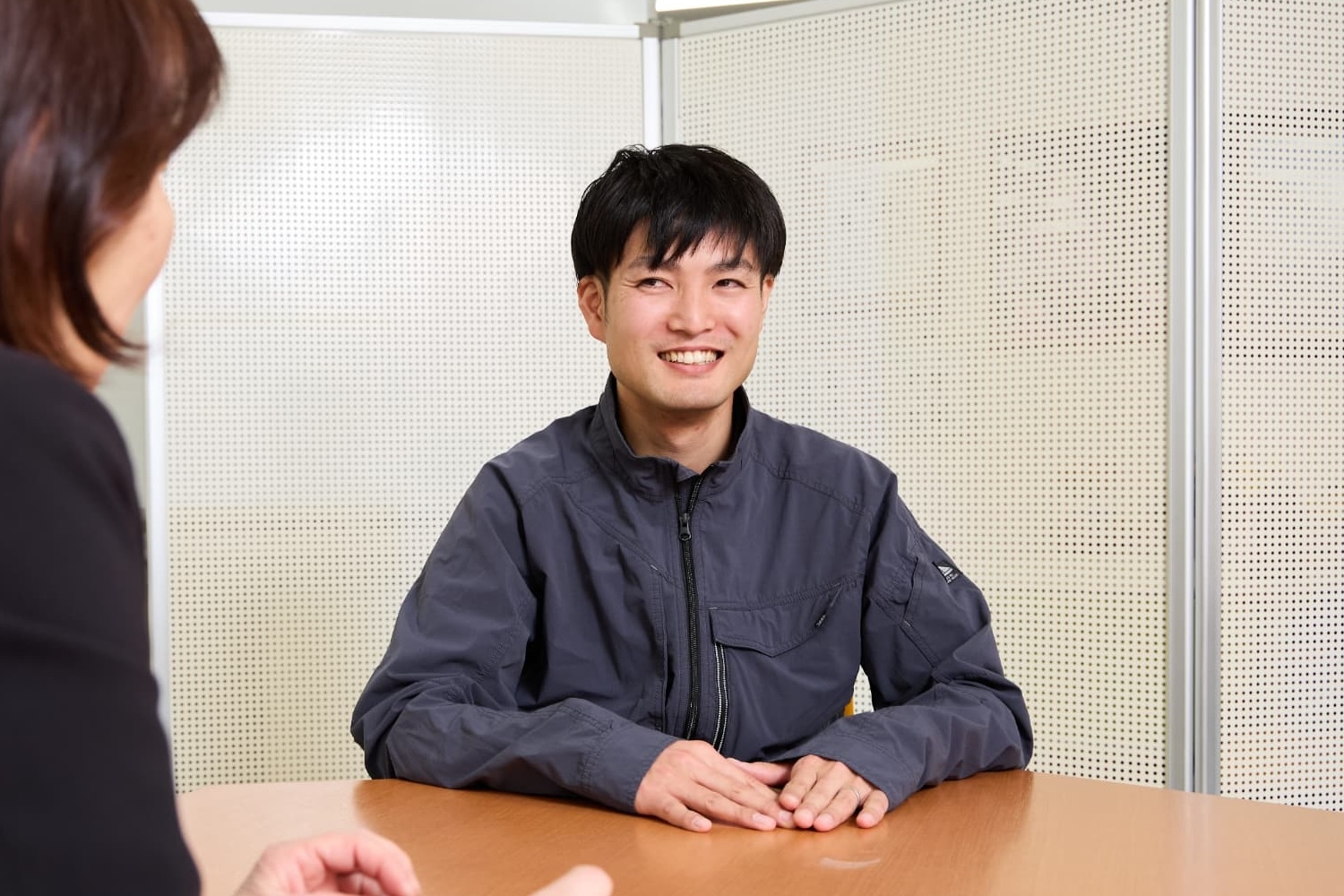
―――仕事と家庭を両立するために、仕事で心がけていることや工夫されていることはありますか?
Oさん 以前から自分に課しているルールは「今日の仕事は明日に持ち越さない」こと。時間に追われて仕事を翌日に持ち越すと次の日はもっと大変ですし、家族に急なトラブルが起きて翌日は仕事ができない事態もあり得るので、今日できることは今日終えなければいけません。
「どうすればもっと業務を効率化できるか」「もっと時短できる方法はないか」ということは、常に考えています。ただ、管理職としての私の業務は自分だけでは完結しないものも多く、自分の業務だけでなく全社的な業務改善まで視野に入れて考えていかなければならないと思っています。
Aさん 私が心がけているのは、できるだけ早く仕事を終えること。私の場合、勤務時間は自分の裁量に任されているので、早朝のうちに事務仕事を片づけて、午後4時頃に仕事を終えることもあります。夕方前に仕事を終えれば、子どもの入浴や夕食の時間も前倒しでき、早い時間に子どもが寝ついてくれて夜の時間に余裕ができるからです。仕事では「時間単位の成果」にこだわっています。限られた時間でいかに効率的に業務を行い、大きな成果を上げるかを意識して仕事に取り組んでいますね。
Tさん 私は、仕事を始める前にその日やることを全部ToDoリストに書き出して、勤務時間内に全て終わらせることを目標にして日々の仕事に取り組んでいます。経理の仕事は1日のスケジュールや業務の締め切りがある程度決まっており、スケジュール通りにこなしていくことが大切です。あとは「何としても終業時間までに今日の仕事をやり終えて帰る!」という気力ですね。メールが届いたらその場で返信するなど、「すぐやる」ことを意識して取り組んでいます。

―――仕事と家庭の両立がしやすいと感じる点や、両立する上で「これはありがたい」と思った福利厚生や社内制度はありますか?
Oさん 何よりもありがたいのは、家庭の事情などを気軽に相談できる上司がいて、相談すると、その人の現在の状況に合った働き方や業務を一緒になって考え、解決策を提示してもらえることです。一緒に働く職場の仲間も理解があり、私が急に出社できなくなったり早退しなければならなくなったりした時も、家庭のことを優先するよう協力してくれます。これまで家事を一手に担っていてくれていた義母が倒れ、今はかなり大変な状況ですが、職場の理解と協力のおかげで何とか仕事を続けることができています。
Aさん 相談できる上司がいて、職場のメンバーの理解と協力があり、いろいろとサポートしてもらえるのは、私も同じです。直属の上司だけでなく、当社では外部のメンタルコーチに相談できる制度もあります。秘密保持がしっかりしていて相談内容が人事評価につながることもないので、安心して相談することができます。会社の外にも相談相手がいるのは、心強いですね。
また、当社の場合、制度の枠にはまらない形で、個々の事例に応じて柔軟に対応してもらえることが、大きなメリットだと思います。例えば、私が九州で行なったリモート勤務は、当時は制度化されていませんでしたが、私が半ば実験的に実践することで初めて実現しました。上司と相談しながら、その時々の自分の状況に合った新しい働き方にチャレンジしていける点も、当社の魅力かもしれません。
Tさん 私の場合は内勤なので、現場に出なければいけない人たちに比べると時間の融通が利きやすいのが、ありがたいです。子どもが急に熱を出したりした時も、周囲の人たちが「休んでいいよ」「仕事は私たちに任せて」と言ってくれて、本当に温かくていい会社だなと思います。
福利厚生でありがたいのは、子ども手当。子どもがいると何かと出費もかさむので、経済的にも助かっています。
社内に「新日本保育園」や託児所があるといい!?
ワークライフバランス実現のために必要なサポートを考える

―――最後に「仕事と家庭の両立のために、社内で今後こんなサポートがあるといいな」と思うことなどがあれば、教えてください。
Tさん 会社に「新日本保育園」があるといいですね。親のわがままですが、職場で身近に子どもを見てもらえる環境があると嬉しいですし、安心して働けます。当社には、ベビーシッター料金の割引を受けられる制度がありますが、個人的には自宅に他人を招き入れて子どもの世話をしてもらうのに抵抗があって……。わが家の場合、いざとなれば義母に子どもの面倒を見てもらうこともできますが、車で1時間以上かかる場所に住んでいるので、気軽に頼むことはできません。託児所のような一時的なサービスでもいいので、社員の子どもを預かってくれる場が社内にあれば、すごく助かると思います。
Aさん 社内保育園・託児所というアイデアは、いいですね。平日に子どもを預ける場所やサービスは比較的ありますが、土日祝日にスポット的に子ども預かってくれる施設は少ないです。休みの日に子連れで出社して、同世代の子を持つ社員や子どもが社内の託児所で一緒に遊んで交流を深めたりするのも、楽しそうです。
Oさん 私は職務上、社員からの要望を聞いて、社員が仕事と家庭を両立しながら働き続けられるような社内制度やサービスを実現していく側の立場です。親の介護や孫の世話など、中高年の社員が直面する家族の問題については私自身も経験し、会社側のサポートが必要なことを痛感しました。若い子育て世代の社員がどんなことを望んでいるのか、幅広く意見を聞きながら、ワークライフバランスを叶える職場づくりに取り組んでいきたいですね。